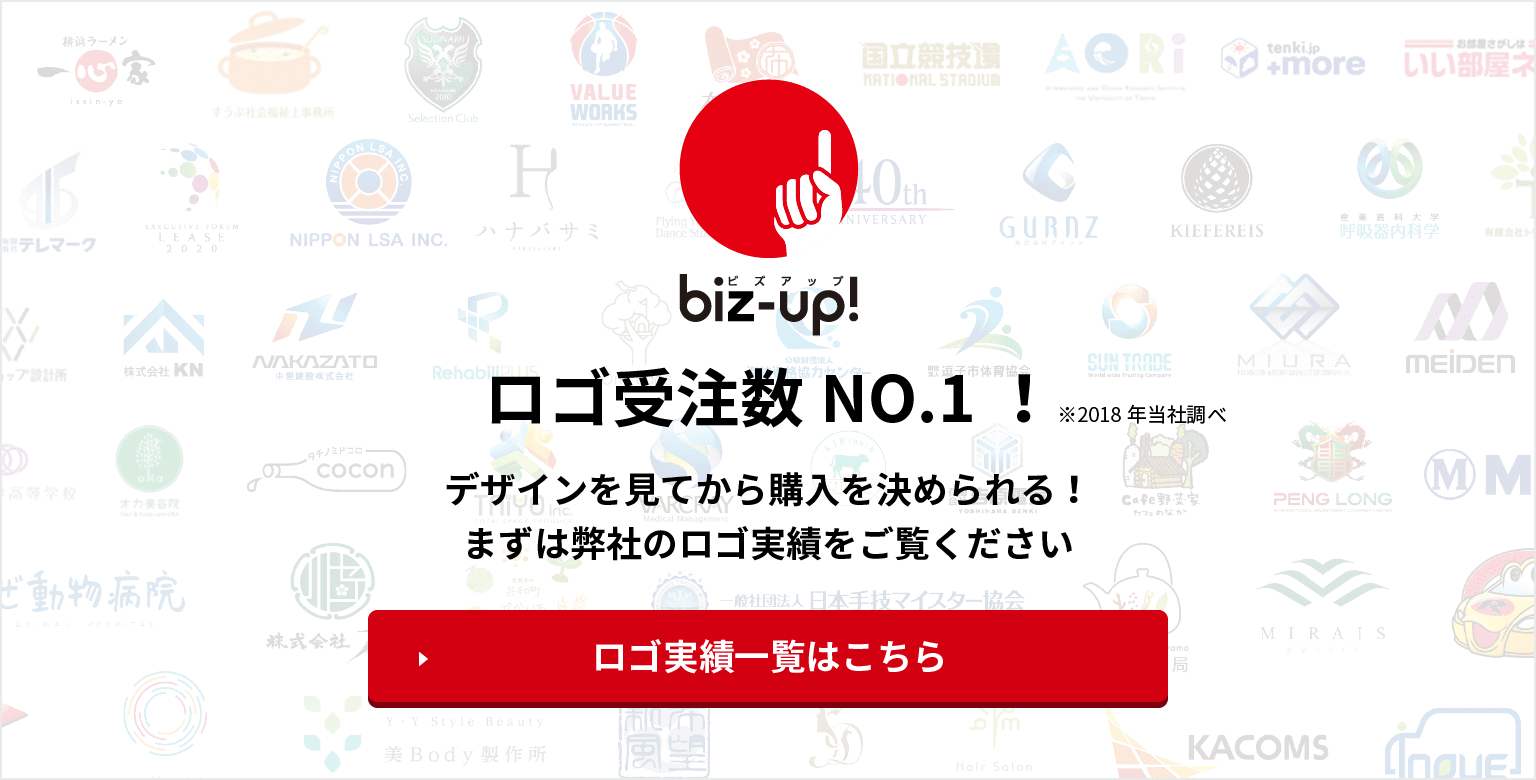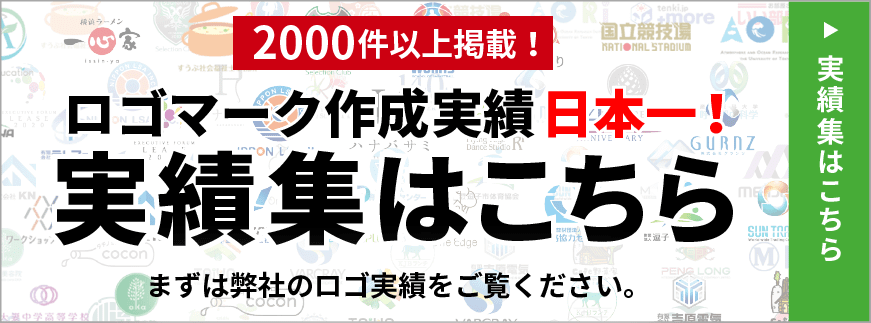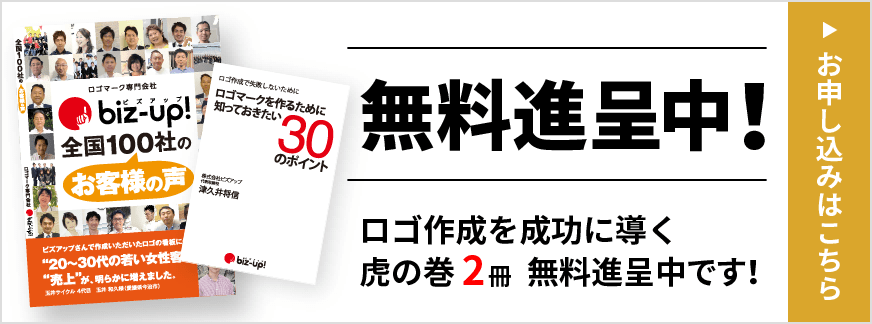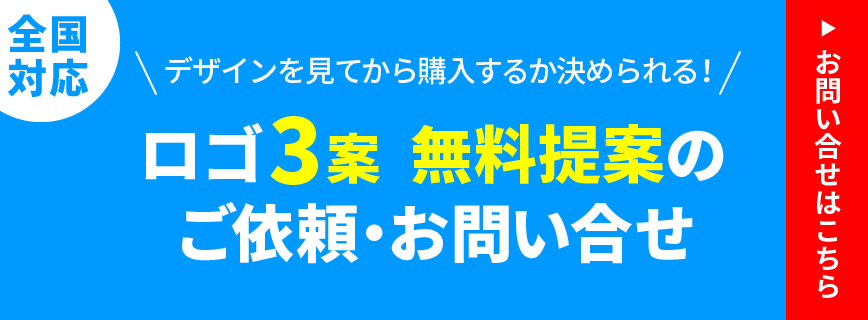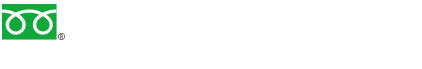ロゴコラムLogo column
「コロコロニュース」をやめてから2ヶ月くらい経ちました。
コロコロニュースを知らない方のためにお話すると、2020年3月にコ□ナがはじまってすぐ(2ヶ月後くらい)にコ□ナのいろんなウソに気づいてしまって、これをみなさんに伝えなきゃ、と思ってはじめた、このコラムの書き出しの一(いち)コーナーです。
内容はコ□ナのことに限らず、メディアや官僚の欺瞞、アメリカや中国の腐敗、そのウラ側にいるヤツらのことなど、政治的な言及もしていました。
このコラムはすでに15年以上書きつづけていますが、コ□ナがはじまる前までは、このコラムで政治色と宗教色は絶対に出さないと決めていました。
しかし、日本が腐っていくのを目の当たりにして居ても立っても居られず、微力ながら発信をしはじめたのが「コロコロニュース」というわけです。
コロコロニュースは5年くらいつづけていましたが、3月末で終えました。それを復活させようというわけではありませんが(毎回たいへんなので。。。)、今日はちょっと動画を一本ご紹介したいと思います。
そして、できればこの動画にある署名活動に署名してほしいなと思います。私のこのコラムでは微力かもしれませんが、被害者の方に少しでもお力添えができればと思いまして。。。
で、何よりもこれ、他人事ではないですからね。明日は我が身の可能性を十分に秘めた問題で、コ□ナ以降、日本が腐っていく様の中心にある問題と言っても過言ではないと思っています。
さて、久しぶりにこんな書き出しとなってしまいましたが、本日はブランディングについて、特に「リブランディング」についてのお話をしてみたいなと思います。
「リブランディング」とか「リスキリング」とか「リ〜〜」って最近はやってますよね。
●「リブランディング」とはなにか、きちんと説明できますか?
いつもお話していますが、「ブランディング」というのは「フワフワ語」です。
「フワフワ語」というのは私が考えた言葉なのですが、みんな「なんとなく」で使っていて、きちんと説明しようとするとできなかったり、人によって解釈にばらつきがある言葉です。
フワフワ語は他にも「コンセプト」なんかもそうです。フワフワ語はこの業界(クリエイティブ業界)まわりの用語に多い気がします。
「ブランディング」って経営者の皆さんは「興味ある!!」とおっしゃるのですが、「ではブランディングって何?」とお聞きすると、みなさん笑って誤魔化します(笑)。
「ブランディング」がフワフワ語なわけですから、「リブランディング」も当然フワフワしてるわな、ということで今回このテーマにしてみました。
で、やはり「リブランディング」を語るには「ブランディング」から説明しないといけないわけです。
「ブランディング」はこのコラムで何度もお話していますが、我々は以下のように定義しています。
- 選ばれるため、選ばれつづけるための施策全般
よく誤解されるのが、「ブランディングは見た目をカッコよくすること」というもの。まったくの間違いではないのですが、それはブランディングの中のひとつの打ち手でしかないわけです。
驚安の殿堂ドン・キホーテはブランディングができていないかといえばまったくそんなことはないです。選ばれたい人に選ばれているからです。
ダサいとかカッコいいとかの話に終止するのは浅いということですね。
では、ブランディングはどうやって行うのか、というと「言葉と画(え)」を使って行います。なので、ブランディングを言い換えると、
- 言葉と画(え)を使って、人々の「感じる」をコントロールすること
といえます。
ブランディングというのはこのような施策を行って「価値を感じてもらう」ことなわけです。「我々の商品は、サービスは、あなたにとって価値がありますよ!」と。
ここで大事なのが、「誰にとっての価値なのか?」ということです。「あなた」って?
これを言い換えるならば「ターゲティング」となります。「ターゲティング」というのは、「あなたは、あなたの会社は誰にとっての価値を提供しますか?」に答えることなわけです。
で、このターゲティングが年々むずかしく複雑になっています。
一昔前(いや、もっと前かな)のターゲティングって、
- 男性か女性か
- 何歳代か
- 職業はなにか
- 年収はいくらか
みたいな情報しかなかったんですよね。ところが、同い年の同じ性別で同じ会社で同じ年収の人同士でも、性格は違います。当たり前ですが。。。
いうなれば、昔のターゲティングって「定量的」だったんですよ。数値化できる項目ばかりというか。
これで成立した時代があるんです。いつもお話していますが、「モノ」「デザイン」「色」の「3つの時代」という考え方があります。この「モノ」の時代は、定量的なターゲティングでもハマりました。
なぜなら、需要のほうが圧倒的に多い時代だったからです。
ところが、供給が増えてくると変わってきます。供給が増えるということは、「競合が増える」ということです。これは消費者から見たら「選択肢が増える」ということになります。
そうすると、消費者は「選択」によって個性を発揮しやすくなります。こうしてどんどんニーズが多様化していったわけです。同じ「冷蔵庫がほしい」というニーズでも、「私はこんな感じのデザインの冷蔵庫がいいわ」とか。
これが進んでいった結果、定量的な分析だけではターゲティングが正確ではないよね、となり、「ペルソナ」といったような様々なターゲティング手法が取り入れられるようになったのが現在です。
何が言いたいかをまとめると、
- ブランディングはターゲティングがとっても大切
- ターゲティングは昔と違ってどんどん難しくなっている
- なぜなら、ニーズが多様化して定量的なターゲティングが効かなくなってきたから
となります。
●「リブランディングしないで!」とお客さまを止めた話
ここで、昔やったお仕事のお話を。このコラムで何回か紹介したことがあります。もう15年近く前だったかな。
ロゴをつくったお客さまに沖縄の老舗のお弁当屋さんがありました。社長は三代目で私と年齢もわりと近く(当時私が30半ばくらいで、その三代目が30手前くらいだったかな)、意気投合して何度かお会いしていました。
つくらせていただいたロゴは評判も良いみたいで、お店の看板はもちろんのこと、ユニフォームや箸袋、レジ袋などさまざまなところにロゴを入れてくださいました。ロゴのデザインはポップで親しみやすいものでした。
あるとき、三代目が言いました。「ブランディングの相談をしたい」。そこで東京に三代目が来たときにランチをしながら打ち合わせをしたんですね。
聞くとどうやらロゴを変えたいんだ、ということでした。もっと洗練されたおしゃれなものに。ポップで親しみやすいとは逆方向です。
いうなれば「リブランディング」したいということです。ロゴを変えるということは、看板やユニフォームなど、さまざまなものも変えるということですから。
もしそうするとなると、デザインから感じる価格のイメージは逆方向。ポップで親しみやすいほうはリーズナブルな印象を与えますが、洗練されたおしゃれなものは高価な印象を与えます。
私は直感的に「それは違う気がする」と思い、ロゴをはじめとした全体的なデザインを変える前に、3回にわたるブランディングに関する調査をさせてくれとお話しました。
そして沖縄に3回にわたって行きました。やったことは3つ。
- 近隣の競合調査
- 上得意顧客へのインタビュー(座談会形式)
- 店舗での顧客の観察
実は近隣の競合調査はそれほど大切なものとは思いませんでした。なぜなら、そのお弁当屋さんはこれから開店するお店ではなく、地元に根づいて一定のお客さんがいるお店だったからです。
つまり、自然とポジショニング、ターゲティングの棲み分けができているということです。
問題は、今のお客さんが「どんな人たちなのか」を解像度高く調べることでした。そのための座談会と店舗での顧客観察でした。
まずは座談会。座談会は、ご高齢のおばあさん(沖縄でいう「おばあ」)が4名と30代の主婦が1名参加してくれました。
おばあたちは口を揃えて、そのお客さまのお店のお弁当や仕出しが「すばらしい」と絶賛してくれました。ボリューム満点でおいしいし、接客もすばらしいと。問題点を探りたかったのですが、とにかく褒めるだけでした。
そんな中、30代主婦の方が一言も言葉を発しません。話しづらそうでした。私が「何かありますか?」と水を向けると、とても言いづらそうに次のように言ったのです。
「すみません、私、こちらの仕出しはよく買うのですが、実は私たちは食べていません。おじい、おばあや子どもたち用にいつも買っていて、自分たちの食べる分はおしゃれな居酒屋とかのテイクアウトを利用しています。。。」
これを聞いて三代目は腰が砕けそうになっていました。そして堰を切ったようにおばあたちも「そうそう!」といってネガティブなことを言いはじめました(汗)。
ボリューム満点でおいしいっていっていたのに、「量が多すぎる」とか(泣)。「そうそう!」じゃないよ、こちとら「涙そうそう」だよ(沖縄だけに)、という感じ。
この座談会の内容から、特に30代の主婦がおしゃれな居酒屋でテイクアウトしているという情報から、洗練されたおしゃれな見た目に店舗のイメージを変えるべき、と結論付けてしまいそうです。しかし、私はおそらく違うだろうとまだ思っていました。
翌日、お昼前から店舗の一角に立って、来店するお客さんを観察しました。予想通りというかなんというか。。。
お客さんはほとんどが2タイプに分かれていました。
- ブルーワーカーの方々で、仕事柄ガッツリ系の食事を求めている
- 30代くらいの女性で太っている(めっちゃ食べそうな人)
もちろん他のタイプもいましたが、目立ったのはこの2タイプでした。そりゃそうですよね。ポップで親しみやすい見た目、ボリューム満点なのにリーズナブルな商品たち、このような人たちに「選ばれるための施策」をしていると言っても過言ではないわけです。
そこで私は次のように進言しました。
「今のブランディングを変えてはいけません。変えたいなら、別のブランドを立ち上げてください。」
「別のブランドを立ち上げてください」とは言ったものの、お客さまであるそのお弁当屋さんが本当に実行できるかは未知数でした。時間も人もお金もかかりますから。
つまり、私にとっては「今のブランディングを変えて洗練されたおしゃれなやつにしちゃいやしょうよ!」と言ったほうが儲かったんです。でも言いませんでした。これがきっと信頼となって返ってきて、新しいお仕事を生んでくれると思ったから。
なぜ「別のブランドを立ち上げてください」と言ったかというと、今のブランディングを変えてしまうと今のお客さんが来なくなるからです。
座談会に来てくれたおばあたちも、ガッツリ系のお兄さんたちも、ぽっちゃり系の女性たちも、今のそのお弁当屋さんの利益をもたらしてくれている人たちが来なくなる可能性があるわけです。
座談会に参加してくれた30代主婦の方は、ある種の価値があると思っているからそのお弁当屋さんの仕出しをよく買うわけです。
「自分たちで食べる」という価値ではありませんでしたが、おじい、おばあ、子どもたちはそれで満足するという価値です(誰にとっての価値なのか)。
なので、その価値を欲してくれている人たちのためにも、今のブランドはそのまま残して、やりたいことは新しくやってください、と伝えたわけです。
その後、そのお弁当屋さんは別のブランド(ケータリング)を立ち上げました。しっかりと「洗練されたおしゃれな」ブランディングで。
このコンサルは今でも成功だと思っています。その新しいブランド(ケータリング)の仕事を発注してもらえなかったことを除いては(爆)
●今までの顧客を捨てる覚悟はありますか?
本日のお話のテーマはブランディングではなく「リブランディング」でした。ここまで読んでいただいて、リブランディングについてわかりましたでしょうか。まだ解像度が低いですよね、きっと。
では、「リブランディング」とはなにか、答えをお話しちゃいますね。
多くの人が、リブランディングというのは「見た目の印象を変える」ということだと思っていると思います。それも間違いじゃないんですが、じゃあ、見た目の印象を変えるとどうなるかわかっている?と言いたい。
それが先ほどのお弁当屋さんのお話です。見た目を買えちゃうと、ターゲットが変わっちゃうんですよ。「誰にとっての価値なのか」の「誰」が変わっちゃうの。だから軽々しくやったらダメなんですね。
つまり、「リブランディング」を定義するならば、
- ターゲットを再設定すること
- 「誰にとっての価値なのか」の「誰」を再定義すること
こういうことなんですよ。これがリブランディングの本質なんですよ。
ということは、リブランディングするなら「今までの顧客は捨ててください」ということなんですよ。それくらいのことなんですよ。
「いやいや、そんな見た目の印象を変えたくらいで大げさな」と思うかもしれませんが、その見た目がいかに強力かはこのコラムでは何度もお話してきました。
- 体験したことがない商品、サービスは「見た目」しか判断基準がない
- 人は必ず見たものから何かしらの「印象」を持ってしまう(デザインの無拒否性©)
「有名シェフの料理も無造作にビニール袋に放り込まれていたら残飯に見える」というのは、つい先日お伝えしたばかりです。
たとえばカンタンな実験ですが、以下の画像の右と左、どちらが好みですか?

どちらが好みでもいいんですけど、これはAIにつくらせた同じ女性の画像です。見た目が違うだけで好みがはっきりと分かれるはずです。
左とは付き合いたいけど右とは付き合いたいと思わないという男性、右なら友だちになりたいという女性、さまざまだと思います。明らかに行動に影響を与えていますよね。
もちろんどっちも好き、みたいな人もいるでしょう。そういう人はぶっちゃけ放っておけばいいんです。ビジネスにおいてはリブランディングしてもお客さんのままでいてくれるような人です。
問題はそれ以外です。見た目によって消費者が行動変容するというのは、本当に重要なことなんです。
さて、リブランディングの事例も少しお話しておこうと思います。
そもそもリブランディングが行われるのは以下のようなケースが考えられます。
- 陳腐化してきた
- 事業をピボットした
- 事業領域が変わった(拡大された)
- なんとなく経営陣の気分
まあどのケースでもいいんですが、「今のお客さんを捨てる覚悟はありますか」というポイントだけは押さえておきたいところです。
たとえばブランドをいくつも持っていて、それとは別にブランドを包括するコーポレートのリブランディングをするような場合は、顧客を喪失するリスクをそれほど考えなくても良いかもしれません。
しかし、そういうケースはほとんどが大企業が行うことです。中小企業は十分な注意が必要です。リブランディングをすべきなのか、それとも新しいブランドを立ち上げたほうが良いのか、よくよく検討すべきということですね。
リブランディングをすべきときというのは、私は「陳腐化してきた」ときであるべきだと考えています。
有名なリブランディングの例としては、「マイルドセブン」が挙げられます。はい、タバコの。
知っていました?今の若い子たちに「マイルドセブン」といっても一部の子たちにはすでに通じないということを。。。「メビウス」っていわないといけないんです。
もうこの時点で私はリブランディングが成功したと言っていいのではないかと思っているのですが、「マイルドセブン」は今はなく、「メビウス」というブランドに変わっていることは、喫煙者(または元喫煙者)であればご存知のことと思います。
メビウスにリブランディングしたのは、2012年。当時は「なんでマイルドセブンからメビウスなんていうよくわからないネーミングに変えるんだろう?」と思っていました。
また、広告も若者がスノーボードをしているような広告で、明らかにターゲットが20代前半だと感じさせるものでした。
めちゃめちゃ違和感を感じたのですが、ほどなくしてその理由が私の中で明確になります。
以下は私の推測であり、ChatGPTに聞くと違う答えが返ってくるのですが、私は自分の推測のほうが正しい、または結果的に私のいう効果が生まれていると考えています。
マイルドセブンの歴史は古く、1977年だそうです。私が物心ついたころには、うちのオカンはマイルドセブンを吸っていました。ずっと吸ってたなー。私がビズアップをはじめて何年も経っても。
言いたいこと、わかりますでしょうか。
マイルドセブンは、私の親世代から我々の世代までに大ヒットしたタバコなんです。ブランドは我々の親世代とともに育ち、そして我々子どもの世代とともに陳腐化していく宿命だった。
JT(日本たばこ産業)はこれを見抜いていたんだと思うんです。次の世代までにはマイルドセブンのブランド価値を持ち越せないと。
で、このまま座して死を待つよりも、今のターゲットをすべて捨ててリブランディングしよう、というのが2012年のリブランディングの動きだったと私は考えています。
おそらくこのリブランディングは成功しています。不思議なもんですが、うちのオカンはメビウスになってからタバコを変えたんです。
ちなみに、JTの公式発表によるとマイルドセブンからメビウスになっても「味の変更は行われていない」ということです。つまり、味ではなく「見た目」が与えた影響により、ブランドスイッチが起こったというわけです。
もっといえば、見た目によって「味が変わった」とすら思われていたようです。
これもよくこのコラムでお話していることです。見た目により味の感じ方まで変わってしまうのは、実はよくあることなんです。
おもろいですね。どういう見た目にするか、どういう言葉を伝えるかによって、ターゲットが変わってしまうというのは。
このリブランディングの観点からも、経営者であればブランディングをおそろかにするなんてことは考えられないですよね。
ブランディングを何もしていないということは「何もしない会社です」という情報を発信してしまっているわけですから(デザインの無拒否性©)。
今回はここまでです!
津久井
投稿者プロフィール
-
ロゴ専門デザイン会社ビズアップを2006年に創業。
かつてバンドで大手レコード会社よりCDリリースするも、大事なライブ当日にメンバー失踪、バンドは空中分解。その後「社長になりたい」と思いすぎてヨメの出産5ヶ月前という非常識なタイミングで、各方面から非難を受けながらも独立、5ヶ月でビジネスを軌道に乗せる。
2009年から毎週書きつづけているコラムでは、ブランディングやデザイン、クリエイティブについてかなり独特な視点で切り込む。レインボータウンFMでパーソナリティも務めている。
最新の投稿
 カテゴリ一覧
カテゴリ一覧
 関連記事
関連記事
ご依頼・ご相談・
各種お問い合わせは
こちらです
インターネットの手軽さを最大限に活用しつつ、インターネットのデメリットである「顔が見えない・声が聞こえないやり取り」を極力排除した「出会いはデジタル、やり取りはアナログ」が私たちの目指すサービスです。ご依頼やお問い合わせは以下のフォーム、またはお電話で可能です。
-
フォームからのご依頼・
お問い合わせ24時間受付中